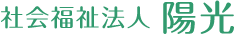トップページ > みかんの丘 特別養護老人ホーム
みかんの丘 特別養護老人ホーム
2025年度 法人事業計画
年間目標:介護DXの実現
①財務の視点
- 電子同意やオンライン面会などの導入を記載したリーフレットを作成し、遠方(東区・北区・南区)の営業活動に使用する。
- HPの「利用様の声」に退所されたあとにご家族にアンケートを実施し、その声をHPに反映する。
- HPの新着情報欄に待機者や空床の案内などの情報発信していく。
- SS利用者受け入れ時に体調確認・検温等の確認を徹底し、利用者のマスク着用をすすめる。
- 介護職においては月末にフリー勤務者を配置する。
- コメディカルにおいては毎月勤務計画を立て、個人が勤務管理を徹底する。
②顧客の視点
- 骨折・肺炎による入院者を出さないためにヒヤリハットの共有と対策をユニット会議にて検討する。
- 機能訓練をテーマした研究に取り組み、ADLの向上を目指す。
- 特養カンファを各ユニット会議の時間に実施し、議事録に追加でカンファレンス内容を記載する。
- JOYSOUND機材を用いた口腔体操を夕食前の時間に実施する。
- 口腔ケアの勉強回を5月と11月に実施する
- サロンチームをつくり、内容・意向・傾向を検討する機会を月に1回設ける。
- インスタチームをつくり、内容・傾向を検討する機会を月に1回設け、月に2回投稿を実施する。
③業務プロセスの視点
- 担当者会議で電子同意のメリットを説明し、ご家族と一緒に登録作業を実施する。
- 郵送が多い方などにはLINEや訪問にて電子同意のメリットを説明し導入を促す。
- ノーリフティングケアの勉強会・研修会への参加を行う。
- 負担軽減に対するアイデアを出しあう会議を5月に実施する。
- 通常の入浴担当とは別に日半スタッフを2名配置する
- スケジュール表を作成し、実施項目箇所を確実に清掃できるようにリーダー会議にて周知をはかる
- 毎月福祉用具の管理を徹底し、破損等が起きないようにユニット会議にて周知を行う。
④人材と変革の視点
- スタッフインタビューを2名撮影を行う。
- 福利厚生の充実を図る為にアンケートの実施を行う。
- 外国人スタッフとの勉強会を7月と12月に実施する。
- 他法人との意見交換ができる研修等の案内があった際には参加できるように調整を行う。
- 全国ケアコンテストの参加を行う。
- 精神的ケア、看取りケア、褥瘡ケアの勉強会を年間予定表に沿って行う。
- 常勤日本人スタッフは7月10月3月とし、非常勤スタッフ・外国人スタッフは8月11月4月とする。
熊本県福祉サービス第三者評価結果公表基準
|
|
詳しくはこちら(PDFファイルで開きます) |
概要
| 利用対象者 | 介護度1~5の介護認定を受けられた方 |
|---|---|
| 利用定員 | 50名 全室個室 |
全室個室によるユニットケア方式を採用しており、家庭的な環境づくりを行っています。
各ユニットには、ミニキッチン・談話室・温泉を利用した浴室を完備しています。

運営方針
根拠ある介護を取り入れ「治療する介護」を達成する為に以下を目指します。
- 1.オムツ使用率ゼロ%達成
- 2.要介護4の利用者の歩行達成
- 3.常食化 胃ろうゼロ達成
- 4.認知症周辺症状改善の達成
- 5.利用者一人ひとりにあった水分量を設定し提供する